|
|
| 京都三条大橋 ~ 大津宿(第53番) |
'18.1.13 10:20
①三条大橋・・・京都市中京区
東海道五十三次の西の起点
現在の橋は本体はコンクリート製だが欄干は木製
今回のウォークもここからスタート |
 |
②弥次喜多像・・・京都市中京区
三条大橋の横に江戸時代、十返舎一九の「東海道中膝栗毛(ひざくりげ)」の主人公弥次さん、喜多さんの銅像がある。
像が建てられたのは古い時代ではなく1994年とのこと。 |
 |
③三条大橋から始まる旧東海道は今の三条通りに沿って東に進む |
 |
④坂本龍馬、お龍「結婚式場」跡
・・東山区三条通白川橋東入南側
当地は青蓮院の旧境内で、その塔頭金蔵寺跡。
元治元年(1864)8月初旬、当地本堂で、坂本龍馬と妻お龍は「内祝言」、すなわち内々の結婚式を挙げた。
この地が選ばれたのは、お龍の亡父楢崎将作が青蓮院宮に仕えた医師であったためと思われる。その縁により金蔵寺住職智足院が仲人をつとめた 。 |
 |
⑤粟田神社・・・京都市東山区粟田口鍛冶町1
スサノオノミコト・オオナムチノミコトを主祭神として祀り、厄除け・病除けの神と崇敬される。京都の東の出入口である粟田口に鎮座するため古来東山道・東海道を行き来する人々は旅の安全を願い、また道中の無事を感謝して当社にお参りされ、いつしか旅立ち守護・旅行安全の神として知られるようになった。 |
 |
⑥粟田口刑場跡・・京都市山科区厨子奥花鳥町
古来、都と郊外の境界に位置するこの地には公開処刑場が設けられていた。
江戸時代には粟田口刑場として処刑が行われ、明治維新後に廃止された。
この辺りは現在の143号線に沿ってかなりの登りが続く |
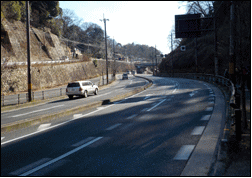 |
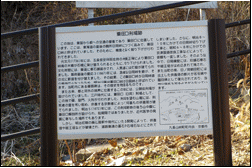 |
⑦車石広場・・京都市山科区厨子奥花鳥町1-1
江戸時代、大津の港に荷揚げされた米などの物資は、牛車(うしぐるま)によって東海道を京都まで運ばれていた。しかし当時の街道は土道だったので、雨が降れば牛車の車輪が泥道に埋まり、思うように通行ができなかった。そこで、今から約200年前、牛車の車輪がぬかるみにはまらないよう、大津-京都間3里(約12km)の道に、両輪の幅に合わせて2列に石を敷くという、一大土木工事が実施された。敷かれた石には、頻繁な牛車の通行によって擦り減り、U字型の凹みが残された。その石がいつの頃からか「車石」と呼ばれるようになった。ここには当時使われていた車石を使って牛車道を再現している。 |
 |
⑧京都市山科区北花山山田町 付近
現在の143号線から分かれて非常に狭い道になる旧東海道 |
 |
⑨五条別れ道標・・・京都市山科区御陵中内町
北面に「右ハ三条通」、東面に「左ハ五条橋 ひがしにし六条大佛 今くまきよ水道」と書かれており、1707年に沢村道範によって建立されたもの。 |
 |
⑩徳林庵・・・京都市山科区四ノ宮泉水町16
南禅寺第260世住職の雲英正怡禅師によって1550年に創建された、臨済宗南禅寺派、山号は柳谷山。
六角堂は江戸時代の作で山科廻地蔵を安置している。はじめ伏見六地蔵にあった六地蔵尊像は後白河天皇の信仰を受け、平清盛・西光法師らの手により、厄病退散、都往来の路上安全、庶民の福楽利益結縁を祈願し、それぞれの街道の入口六ヵ所に六角堂をつくり一体ずつ分置された(1157年)。
六地蔵とは、
・奈良街道 大善寺の伏見六地蔵
・大坂街道 浄禅寺の鳥羽地蔵
・丹波街道 地蔵寺の桂地蔵
・周山街道 源光寺の常盤地蔵
・鞍馬街道 上善寺の鞍馬口地蔵
・東海道 徳林庵の山科地蔵 |
 |
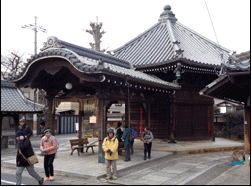 |
⑪滋賀県大津市横木あたりの旧東海道
一号線で分断されたため歩道橋で繋がっている |
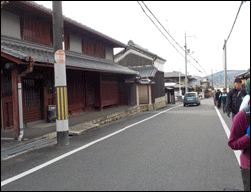 |
 |
⑫閑栖寺
・・滋賀県大津市横木1丁目2-2
浄土真宗大谷派の寺院。
閑栖寺の面する旧東海道は、江戸時代に荷車を運ぶ牛車のために大津から京都にかけて「車石」が敷かれていた。明治期の道路整備によって撤去された車石敷設を、当時の資料をもとに境内の一画に再現している。 |
 |
 |
⑬追分道標
・・滋賀県大津市追分町4−8
東海道と伏見街道との三叉路。
右は山科経由で京都へ。左は伏見、淀、守口を経て大阪へ通じる。 |
 |
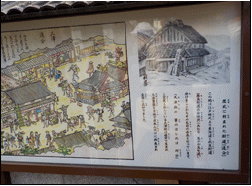 |
⑭月心寺・・・滋賀県大津市大谷町27-9
京、大津への玄関口、逢坂山の関所を控える、かつては東海道随一の賑わいをしていた追分の地で繁昌していた走井茶屋の跡。境内には今も枯れることなく走井の名水が湧き出ている。
歌川広重が描く「東海道五十三次」で、溢れ出る走井の水のそばの茶店で旅人が休息しているのが見られる。その茶店がこの月心寺である。 |
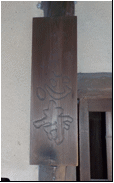 |
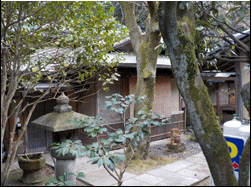 |
⑮滋賀県大津市大谷町
この辺りは東海道(現在の1号線)、京阪電気鉄道京津線、名神高速道路が並んで走っている。 |
 |
⑯逢坂関記念公園・・滋賀県大津市大谷町22
逢坂関(おうさかのせき、あふさかのせき)は、山城国と近江国の国境となっていた関所。相坂関や合坂関、会坂関などとも書く。
東海道と東山道(後の中山道)の2本が逢坂関を越えるため、交通の要となる重要な関であった。その重要性は、平安時代中期(810年)以後には、三関の一つとなっていた事からも見てとれる。 |
 |
 |
⑰関蝉丸神社上社
・・滋賀県大津市逢坂1丁目20
社伝によれば、弘仁13年(822年)に小野岑守が旅人を守る神である猿田彦命と豊玉姫命を逢坂山の山上(上社)と麓(下社)に祀ったのに始まるという。
平安時代中期の琵琶法師で歌人として知られた蝉丸が逢坂山に住んでいたことから、その死去後に彼も上社と下社に祀られるようになった。天禄2年(971年)には円融天皇から下された綸旨により、以後歌舞音曲の神としても信仰されるようになった。 |
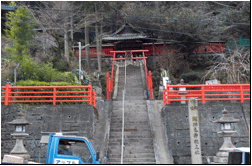 |
⑱ 安養寺
・・大津市逢坂1丁目18−11
本堂には重要文化財阿弥陀如来坐像が安置されている。
また蓮如上人の旧跡で、上人「身代わり名号石」が残っている。
なお境内の「立聞観音」は古く東海道名所図会等に記載されて有名である。 |
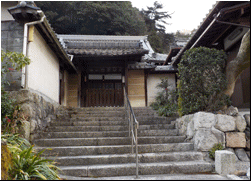 |
 |
⑲関蝉丸神社下社
・・大津市逢坂1丁目15-6
前述の通り蝉丸神社は歌舞音曲の神としても信仰されるようになり、現在でも芸能人が参拝に訪れている。 |
 |
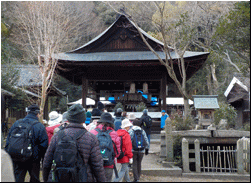 |
⑳大津宿本陣跡・・・滋賀県大津市御幸町6
大津宿では大坂屋嘉右衛門(大塚本陣)、肥前屋九左衛門の2軒の本陣と播磨屋市右衛門の脇本陣が八丁筋に置かれていた。八丁筋には旅籠などが多数軒を連ね旅行く人々を迎えていた。現在は本陣に関する遺構等は残っておらず大塚本陣のあたところに明治天皇聖跡碑が建つのみ。江戸時代当時の本陣は広く、3階の楼上からの琵琶湖の眺めは絶景だったという。 |
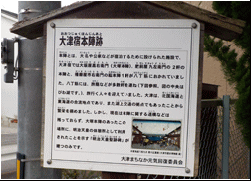 |
21. 露国皇太子遭難地の碑
・・滋賀県大津市京町二丁目2
明治24年(1891年)5月11日、日本を訪問していたロシア帝国の皇太子ニコライを警護をしていた巡査・津田三蔵が皇太子にサーベルで斬りかった。
皇太子は顔に怪我をしただけで命に別状は無かったものの、頭蓋骨に裂傷が入り、後遺症として頭痛が残ってしまった。天皇自らが直々にニコライ2世を見舞う事態となった。
|
 |
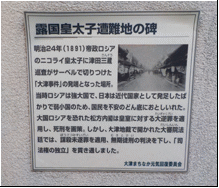 |
22. 滋賀県大津市京町3丁目
向かいの細い道が旧東海道。次回はここから入る予定。 |
 |
23. 大津駅前公園・・ 滋賀県大津市京町3丁目1
今回の終点
(黄色いバスで岡崎へ帰ります)
'18.1.13 16:10 |
 |
|
|